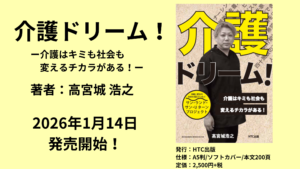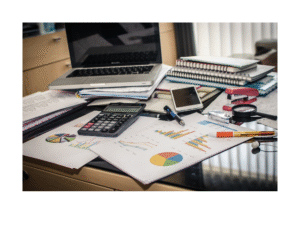介護の世界のビジネスマナーは当たり前じゃない

間代さんの本で
僕がとても好きだったのは、
サ責の専門的な業務内容だけでなく、
「ビジネスマナー」の部分が
とても丁寧に書かれていたことでした。
・あいさつ
・電話の応対
・名刺の渡し方
文字にすると、研修などでよく聞く
ビジネスマナーのようですが、
介護の現場ではこの「マナー」が、本当に奥深いんです。。
1.ググれば出てくる…で終わらない現実
正直、あいさつや名刺交換なんて「ググれば出てくる」内容です。
でも、介護の現場で
その知識を“実際に使えるかどうか”は、まったく別の話。
たとえば、想像してみてください。
あなたは訪問介護のサ責です、今日はご利用者との初回訪問。
Q1. ご利用者宅に着きました。自分の車はどこに停めるのがベストですか?
Q2. ケアマネさんがまだ来ていません。あなたならどうしますか?
Q3. ご利用者が中から手招きしています。あなたはどうしますか?
Q4. 和室で名刺を渡すことになりました。畳の場合のマナーは?
Q5. 身内への選挙投票を頼まれました。あなたはどう答えますか?
……どうですか? ちょっと笑っちゃうような内容でしたかw
でも、実際に訪問介護では「あるある」な場面なんです。
2.介護には“正解”がありません
もちろん、介護保険制度に沿ったサービス提供が大前提です。
でも現場では、「制度通りにやれば正解」とは限らない。
Aさんにとって喜ばしいことが、
Bさんには苦痛になることが、平気であるからです。
だからこそ、介護の世界では、
制度やマニュアルだけではなく、
人と人との関わりの中で「どう振る舞うか」という判断力が問われます。
さらにサ責の仕事は、そんな複雑な介護の現場の“橋渡し役”。
ケアマネさん、ヘルパーさん、ご利用者、ご家族。
関わる全ての人との距離感を考えながら、
その都度ふるまいを選ばなければいけない。
マニュアルに書ききれない判断や配慮が、
毎日のように求められるのがこの仕事の難しさです。
3.一人で現場に立つヘルパーさんにも届けたい
訪問介護は、基本的にヘルパーさんが一人でご利用者のお宅に伺います。
もし何か判断に迷っても、誰かにすぐ聞けるわけではない。
いわば、“戦場にひとりで立つ”ような状況です
間代さんの著書のビジネスマナーからは
そうした一人で戦うヘルパーさん、サ責への
温かなまなざしを僕は感じました。
あいさつひとつ、言葉遣いひとつで、
ご利用者やそのご家族との信頼関係が築けることもある。
逆に、それをひとつ間違えば、
サービス継続に大きな影響を及ぼすこともある。
先ほど挙げた、5つの質問
間代さんの本を読んで、ぜひご自身で答え合わせをしてみてください。
介護の現場でこそ、マナーの力は大きな武器になります。